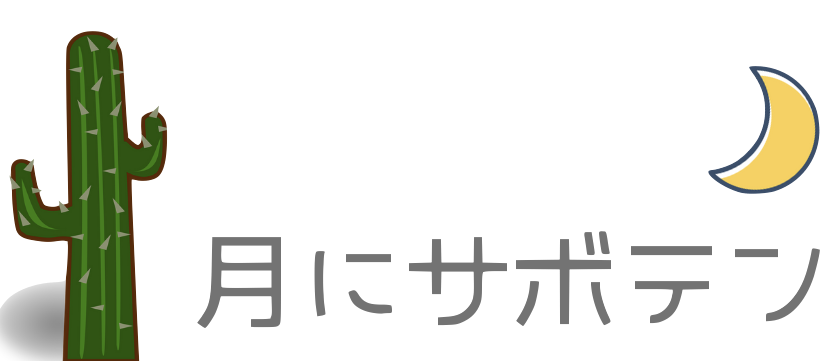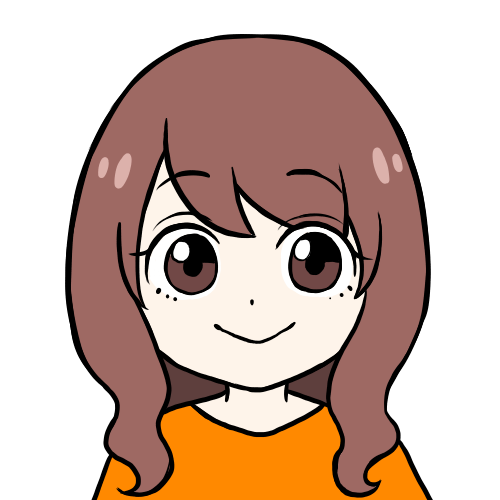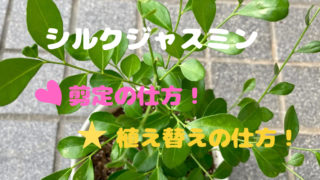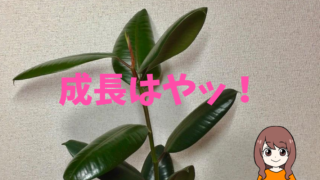鑑賞用トウガラシの育て方のポイント!土選びや鑑賞期間、冬越しも解説します

鑑賞用トウガラシは、色とりどりのカラフルな実をたくさん付けます。
ところで、観賞用トウガラシが元気に育たなくて困っていませんか?
もしかしたら育て方が悪かったせい?と悲しくなってきますよね。
ところが、観賞用トウガラシは、初めてでも割と簡単に育てられます。
そこでこの記事は、観賞用トウガラシの育て方のポイントについて書いてみようと思います。
目次
鑑賞用トウガラシの育て方のポイント

こちらは、うちで育てている観賞用トウガラシです。まるでトンガリ帽子みたい♪
観賞用トウガラシは割と育てやすい方なので、植物をあまり育てたことがない園芸の初心者でも簡単に育てられますよ。
育て方のポイントを抑えて、少しでも元気に育ててみてくださいね。
それでは、観賞用トウガラシの育て方のポイントを解説してみることにします。
日当たりや置き場所
観賞用トウガラシは、日当たりや風通しの良い場所で育てるようにします。
日当たりの悪い場所で育てると、せっかくのカラフルな実も色が悪くなってしまいます。
また、観賞用トウガラシは夏の暑さには強い方です。さすがに強い西日には、あまり当てない方がいいですけど・・
それに、強い日差しに長時間当てると、鉢の中が蒸れて根も傷んでしまいます。真夏は西日が当たる場所に置かないようにしましょう。
どうしてもという場合は、日除けグッズなどで少しでも日差しを遮るようにしてみてください。
水やりの仕方
観賞用トウガラシは、鉢植えで育てるなら水やりは土の表面が乾きかけた頃にタップリとします。
根をあまり深く張らないので、乾燥に弱い性質です。土を乾かし過ぎないように気をつけましょう。
夏場は暑さで土が乾きやすくなります。水やりも、毎日のように必要になってきます。置き場所によっては、朝晩に2回必要なことも・・
肥料の与え方
観賞用トウガラシは、花や実をたくさんつけるためにも肥料が欠かせません。
肥料は、生育が旺盛な5〜9月頃までは定期的に与えるようにします。固形の緩効性肥料と液体肥料のどちらでも良いです。
観賞用トウガラシを植え付けるための用土

プリプリの実がまるでとんがり帽子のよう。
観賞用トウガラシは、植え付ける土によって、根が腐って枯れてしまうこともあります。
土は水はけがよく、また水持ちもほどほどに良い土を使った方がいいです。
私はいつも、もうそのまま使えるこちらの花用の培養土を使っています。

yumeがもう何度もリピートして使っている花用の培養土はコチラ!花もたくさん咲いてきますよ。
土は、もし自分でブレンドするなら下記の割合がオススメです。
赤玉土(小粒)2:腐葉土1の割合でブレンドします。
ブレンドしたら緩効性肥料を混ぜ込んでおきます。
鑑賞用トウガラシの実がシワシワになるのはなぜ?
観賞用トウガラシは、もう実が終わりに近づくとだんだんシワシワになってきます。
もしそうなってきても、もう種を収穫する時期なら、それも自然現象なので仕方がありません。
ところが、もしまだ観賞用トウガラシが生育が旺盛な時期の場合は、日当たりが悪かったり水が不足しているのかも知れません。
時期的に変かも??という時は、その辺のところを改めてよくチェックしてみてくださいね。
鑑賞用トウガラシの実を楽しめる期間は?

観賞用トウガラシを真ん中に記念写真をパシャ!最近は、だんだん秋の気配を感じるようになってきました。
観賞用トウガラシは、小さい花を7月頃から咲かせます。
そして、8月頃には、もう可愛い実を付けた苗がホームセンターなどでたくさん出回り始めます。
観賞用トウガラシの実は、冬の初めの12月頃まで鑑賞できます。というわけで、苗は秋になってから植え付けても、まだ可愛い実を十分楽しめます。
観賞用トウガラシは実がプリプリ。観ているだけでも癒されます。
観賞用トウガラシのお手入れ。注意点を解説!
観賞用トウガラシは、下記のようなことに気をつけて育てるようにします。
実はあくまで観賞用として楽しむだけで食べられない。
刺激があるので、素手でお手入れをした後に目や顔を触らない。
観賞用トウガラシのお手入れは、手袋をつけてからやった方がいいです。
観賞用とはいえ、香辛料のトウガラシと同じようにカプサイシンの成分による刺激があります。肌が弱いとヒリヒリすることもあります^^;
もし小さいお子さんがいたら、ミニトマトと勘違いしてうっかり食べたりしないように気を付けてあげてくださいね。大変なことになっちゃいますので、、
鑑賞用トウガラシは冬越しできるの?
観賞用トウガラシは、夏の暑さには強い性質ですが、冬の寒さには弱いため、一般的には冬越しができません。
そのため、本来は多年草ですが、日本ではほとんど一年草として扱われています。
ところが、室内に取り込んで温度が5℃以下にならないように管理すれば、なんとか冬越しできないこともないそうです。
そこで、12月頃にもう実の鑑賞期間が終わってしまったら、下記のような選択ができます。
- 枝を剪定してから室内に取り込んで冬越しさせる。
- もう一年草としてそのままきっぱりと終わらせる。
というわけで、いずれ上のどちらかを選択することになります。せっかくなので冬越しにも挑戦してみてくださいね。
私は、まだ観賞用トウガラシを冬越しさせてみたことがありません。今年は実が終わってしまったら、せめて種を収穫して保存しておこうかな、と考えています。
追記:観賞用トウガラシは、その後、種を収穫して保存しておきました。そして、冬越しにも初めて挑戦してみることに、、
観賞用トウガラシの種の収穫の仕方や保存の仕方を紹介した記事はコチラ!

観賞用トウガラシの連作障害について
観賞用トウガラシは、連作障害を起こす植物としてよく知られています。
連作障害とは?という疑問にお答えします。
ナス科の植物を毎年同じ土に連続で植えることで、病気にかかりやすかったり育ちが悪くなったりすることを言います。
観賞用トウガラシもナス科です。毎年同じところに植えると、連作障害を起こして育ちが悪くなってしまいます。
ただし、もし鉢植えで育てるなら、多分次は違う土に植えるはずなので、連作障害を起こしてしまう心配はありません。
観賞用トウガラシの花言葉

観賞用トウガラシは、ナスの花によく似た、白色や紫色の小さい花を咲かせます。
花はカラフルな実に比べると、小さくてあまり目立ちません。それでも、花言葉はちゃんと付いていますよ。
観賞用トウガラシの花言葉を下記で紹介します。
- 悪夢がさめた
- 生命力
- 雅味(がみ)
- 旧友
- 嫉妬
花言葉の「雅味」とは、上品で風雅な趣、、、という意味なのだそうです。
最後に
観賞用トウガラシは、冬の寒さに弱いため、一年草として扱われています。
乾燥に弱いので、水を切らさないようにします。そして、できるだけ日当たりの良い場所で育てるようにしましょう。
生育が旺盛な時期には、肥料を定期的に与えると、花や実をたくさん付けるようになります。
観賞用トウガラシは、基本的に冬越しが難しいと言われています。
ところが、室内に入れて温度管理をしたら、必ずしもできない、ということでもないそうですよ。
もし無事に冬越しできなくても、種され収穫しておけば、また翌年に種から育てることもできます。
育て方のポイントに気をつけながら、上手に育ててみてくださいね。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
それではまた・・・